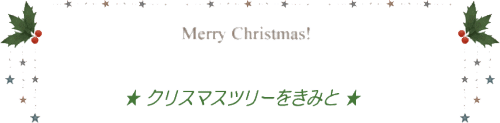 その日、僕がモーツァルトに寄ったのは、ふとした思いつきからだった。駅前のふじみで夕食を済ませた帰り、ついでだから食後のコーヒーを飲んでいこうと思ったのだ。一週間の演奏旅行を終えて欧州から帰国した日のことで、悠季は急な仕事が入って出かけており、僕らは別々に夕食を済ませる手はずになっていた。 富士見町の我が家に帰り着いたのは、まだ夕刻前といった時間で、僕はまずシャワーを浴びてフライトの疲れを洗い流すとスーツケースの荷解きを済ませ、その足でふじみに向かった。夕食には些か早い時間だったが、機内食には殆ど手を付けなかったので腹は空いていたし、一旦座ってしまったら、動くのが億劫になりそうな気がしたのだ。時差の影響に有りがちな眠気は感じていなかったが、全身はなんとなくだるかった。 僕がいわゆる出稼ぎに行く前夜と帰宅した夜、悠季はいつも手間隙かけた手料理の数々を食卓に並べてくれる。彼が「いってらっしゃいディナー」「お疲れさんディナー」と呼ぶそれは、僕を労おうとしてくれる彼の心づくしであり、大変に心癒される嬉しいひと時に違いないのだが。近頃頓に忙しくなってきた彼の負担になってはいないかと気になって訊ねてみたところ、悠季は悪戯っぽく笑って言った。 「普段手を抜いちゃってる分、ポイントを稼げるチャンスはしっかり押さえておきたいな、な〜んてね」 冗談めかしていても、僕には悠季の気持ちが手に取るように解った。僕も同じような思いを抱いていたからだ。 離れている時間が増えるにつれ、気持ちを伝え合い通わせ合おうと努めることの大切さを痛感するようになった。だが、そうと解っていても、慌しい日常の中では物理的にも精神的にもそうした余裕は持ち難い。僕の離日と帰国を一種のイベントのように扱うことで、機会が作れると。そう考えてのことだろう。しかし、義務感を覚えてしまうほどに無理をしては逆効果だ。 「きみのポイントはいつも満杯状態ですので、これ以上稼いでいただいても貯めようがありませんよ。無理をしないと…どうかそれだけは誓ってください」 「うん。この先、どうしたってダメなこともあるだろうし……できるだけってことにするから」 そっと抱き寄せると、悠季も僕の背を柔らかく抱き返してくれた。 そんな話をしていた矢先の、この事態である。 ツアー先のホテルへ急な予定変更を伝えてきた電話で、悠季は「お疲れさんディナー」が出来ないことを酷く残念がっており、何度も「ごめんね」と繰り返した。そんな彼に、僕はふと、一緒に暮らし始めた頃の、家事をすべて担うことに固執していた悠季を思い出し、堪らなく可愛いと思ったのだが――― これはもしや、失言の部類に入ってしまいますかね? 悠季にはどうか内密に。 「では、夕飯はそれぞれに済ませて、風呂上りにワインでも開けましょう。僕を労ってくださるには、きみさえいただければ十分なんですから」 からかいの言葉を付け足したのは、悠季の精神的な負担を慮ってのことであり、きっと顔を真っ赤にして言うのだろう「バカ」と可愛らしく呟く声を聞きたかったからでもあるのだが。 《なに言ってんのさ。そんなの、とっくに織り込み済みだろ?》 言い負かされてしまった。 なんというか……やはり逞しくなったものである。 さて。 そんなあれこれを思い出しながらくちくなった腹を抱えて家路を辿るうち、僕は食後のコーヒーも済ませて帰ろうと思いついた。自分だけのために淹れるのは正直なところ面倒だったし、独りでコーヒーを沸かして飲んだ形跡など、残さない方がいいように思えたのだ。すっかり日の暮れた街は商店を彩るイルミネーションの所為で、むしろ昼間よりも賑々しい。流れてくるクリスマスソングも道行く人々も浮かれ調子で、なんとも落ち着かない感じだ。モーツァルトの古びた木のドアが見えてきた時、僕はホッと息を吐き、店内に足を踏み入れてほぅ、と肩の力を抜いた。 コーヒーの香り、落ち着いた店内を満たす静かな調べ、石田氏の笑顔。 変わらない温もりで僕を迎えてくれる空気を、ゆっくりと吸い込んだ。 「桐ノ院くん!」 「こんばんは」 「いらっしゃい! ああ、座って、座って! いつ帰って来たの? 今回はヨーロッパだったよね?」 「ええ、ドイツから、今日の午後戻りました」 「そりゃお疲れさんだったねぇ。時差は平気?」 「ええ、飛行機の中でしっかり寝ましたので」 「そう、ならいいけど。 守村ちゃんは、今日は仕事?」 「ええ、打ち合わせの予定が急に変更になったそうで。今、ひとりで晩飯を済ませてきたところです」 「ああ、そうなの。一昨日だったかな、大学の帰りに寄ってくれてね。僕もこのところ練習休んでばっかだもんで、久しぶりに顔を見たんだけど。元気そうで安心したよ」 「そうでしたか」 目の前のサイフォンから盛んに立ち昇る湯気と一緒に芳ばしい香りが漂ってくる。黙っていても出てくる僕の好みの特注ブレンドは―――珈琲専門店であればどこの店でも同じものを頼むのだが―――この店のものが一番しっくりと舌に馴染む気がする。飲み慣れているからだ、というなら、サフランの方が余程回数は多い筈だが。 そんなことを考えながら、サイフォンの中を掻き回す熟練の手つきに見惚れていたのだが―――その手がふと動きを止めた。 「ねえ、桐ノ院くん……身体だけはさ、気をつけてね」 しんみりと呟くように言った石田氏は、少し悲しげな顔で僕を見ていた。 「休む間もないぐらいに忙しいでしょ? だからさ……」 どうやら僕は、彼に酷く心配をかけていたようだ。そういえば、僕がサムソンと契約したことを陰で随分心配していたらしいと、悠季から聞かされたことがあった。 「明日と明後日は僕も悠季もオフですし、それに、最近少しは我侭が言えるようになりましたので、せいぜい休ませろとごねることにします。僕としては、フジミが振れればいっぺんに元気が出るのですが」 僕はそれを、彼に愁眉を開いてもらうためのユーモアとして言ったつもりだったのだが。 「フジミの練習場のためにね、きみたちふたりだけに大変な思いをさせてるみたいでさ……なんかね、心苦しくてね」 僕がサムソンと契約した目的が、練習場建設資金を荒稼ぎすることにあったと、よもや彼は知らないと思うのだが。あるいはこの人のことだから、薄々感じていたのかも知れない。 「それは、僕のかねてからの夢ですし、悠季も同様です。それに、今ではフジミの諸君全員と共有する夢でしょう?」 この店で、僕は初めて抱いていた夢を語った。それは、フジミに出逢えたからこそ見ることの出来た夢であり、悠季はそれに呼応してプロを目指す決意をした。思わず熱くなってしまって石田氏には笑われたものだが、もう随分と昔のことに思える。けれどあの日の高揚感は、こうして思い返せば、まるで昨日のことのように鮮やかに甦ってくる。 「うん……そうだったね」 「その夢があるおかげで頑張れます」 僕は石田氏の目をしっかりと見つめて頷いた。 「は、はは……悪かったね、変なこと言っちゃって。……はい、お待ちどうさま」 差し出されたカップから甘さを含んだ芳ばしい香りがふわりと上ってくる。その香りを楽しみながら静かに一口すすって―――思わずため息が零れた。 「ああ、美味いです」 「そうかい? よかった」 「ええ、懐かしいというか……帰ってきた、という気がします」 そうだ、この店の持つ雰囲気は、帰る場所の、ホームの温もりだ。 僕がずっと持てずにいたホームは、悠季と出逢って彼の居る場所になり、やがてフジミやこの店へと広がり――― 「嬉しいねぇ、そう言ってもらえると。懐かしいって言えばさ、守村ちゃんもね、この間久しぶりにホットドッグを食べて、懐かしいって笑ってたよ」 「そうですか」 「うん、それでね、いろいろお喋りしながら、あのツリーの飾りつけも手伝ってくれてね」 石田氏は店の一角を目で指し示した。その存在には店に入って来た時から気づいてはいたのだが、この季節には別に珍しくもないし、と特に注意を払っていなかった。改めて見てみると、定番のオーナメントと一緒に小さな楽器が幾つもぶら下がっている。僕は席を立ってツリーに歩み寄った。 本物の樅の木に吊るされた小さな楽器たちは、それぞれの材質まで再現された、なかなかに精巧な造りだ。種類も豊富で、オーケストラが組めるだけの一通りの楽器が揃っている。 「これは、元はコレクション用のミニチュア楽器ですか?」 「うん。でもオーナメントにしたら良さそうだなと思ってね、紐をつけたわけ」 「なるほど。二丁目楽団の本拠地に相応しいツリーですね。一通りオケの楽器が揃っているようですし、皆も喜びそうだ」 「でしょ? 守村ちゃんも同じこと言ってたよ。ツリーの飾りつけなんて子供の頃以来でわくわくするって、嬉しそうに手伝ってくれてね」 話の端々に出てくる、僕のいないところで交わされた悠季との会話、僕の見ていない悠季の表情。石田氏を介してそれらを知ることには意外なほど不快感はなく、むしろこの場にいない悠季の存在を感じて、三人で談笑しているような気さえしてくる。僕は童心に帰ってツリーの飾りつけを楽しんだという悠季を思い浮かべ、ツリーを前にはしゃいでいたのだろう子供の頃の悠季を想像し、そして、僕自身の幼い頃の、数少ない幸福な記憶を思い出した。 クリスマスを祝う習慣の無い桐院家にそれを持ち込んだのは、伊沢だった。突然のように用意されたツリーやプレゼントやケーキなどクリスマスのあれこれは、父母からの贈り物だと聞かされはしたが、今思うと恐らくは伊沢の進言に祖父の口添えがあって実現したものなのだろう。前時代的なあの家にあって、僕に世間並みの子供らしい感覚と楽しみを与えてくれんとして。 大人の背丈よりも高い立派なツリーを伊沢と一緒に飾りつけながら、僕では到底届かない天辺の星を自分の手で飾りたいと我侭を言い―――伊沢はそんな僕を抱き上げて、この手で飾らせてくれた。あれは確か、幼稚園に通っていた頃のことだ。 「あの……桐ノ院くん?」 躊躇いがちにかけられた声に、物思いから呼び戻された。 「ああ、失敬。子供の頃のことを思い出していまして」 「あ、そうなの? ならいいんだけど……」 歯切れの悪い物言いに視線で先を問いかければ、石田氏はバツが悪そうに頭を掻きながら白状した。 「いやね、タクトだけ無いからさ、申し訳ないな、と思ってね」 言われてみればその通りなのだが、僕はまったく気にしていなかった。 「そうですね。家から持ってきて吊るしてもいいのですが、あの形はオーナメントとしては間が抜けていて不向きでしょう」 石田氏はぷっと噴き出した。笑いながら、悠季も似たような感想を述べたのだと聞かされ「きみたちってやっぱり感覚が近いんだろうね」と言われ、僕もつられて笑った。なんともいえず胸のうちが温かくなる心地だった。 家に帰る道すがら、僕は楽しい計画を思いつき、それに急かされるように足を速めて我が家に帰り着いた。思ったとおり悠季はまだ帰宅しておらず、僕は暖房を点けるよりも先に電話に飛びつき、成城の実家に掛けて伊沢を呼び出した。何かというと彼に頼ってしまう癖はもういい加減卒業したいと思っているが、ことは急を要するので彼の助け無しに成し遂げるのは難しい。しばらく待たされた後電話に出てくれた伊沢に、忙しい時間帯に掛けた詫びを言ってから頼みごとを話した。 「クリスマスツリーに使う樅の木を手配してもらいたいのです。大きさは僕の背よりも高いもので、出来れば二メートル五十センチぐらい。ピアノ室に置きますので鉢植えになったものを。明後日の午前中に届けて欲しいのですが……大丈夫だろうか?」 《そうですね、自然のものではございますし、今頃は需要も多ございますので、大きさのご希望に添えるかどうかが。圭様のお背よりも高くてお部屋に収まるもの、ということでよろしゅうございますか?》 「ええ、それで結構です」 《かしこまりました。すぐに手配いたします》 「ありがとう。無理を言ってすまない」 《いえ。詳しいお届けの時間が決まりましたら、ご連絡いたします》 それでは、と電話を切りかけて、ふと思いついて呼びかけた。 「伊沢さん?」 《はい》 「昔、一緒にツリーの飾り付けをしましたね。天辺の星を、伊沢さんは僕を抱き上げて飾らせてくれた。覚えてるだろうか?」 《そのようなことも…ございましたね》 「伊沢さん」 《はい》 「ありがとう」 今年のクリスマスも演奏会が入っていて、相変わらずふたりきりの甘い夜には縁のない僕たちだが、慌ただしい日々の中でもツリーを飾ってクリスマス気分を楽しむことぐらいは出来る。明日はのんびり寝坊をして、それから悠季と一緒にオーナメントを買いに行こう。明後日、樅の木が届いたら一緒に飾り付けて。悠季は楽しんでくれるだろうか? そして、天辺の星は――― きみが飾ってください、と悠季を抱き上げたら、彼は怒りますかね? 僕の思い出話を聞かせたら、多分笑って応じてくれると思うのですが。 僕はえもいわれぬ幸福な気分でまだ見ぬ我が家のツリーを思い浮かべ、その横で楽しげに笑う悠季を思い浮かべた。 翌々日、僕の希望どおり、伊沢が手配してくれた樅の木が僕らの家に届いた。 ただ、この家の天井が高いお陰で室内に収めることが適ったその木は三メートルに届こうかという堂々たる姿で、悠季は大きな目を更に見開いてぽかんとそれを見上げ、流石の僕も苦笑するしかなかった。電話の最後に、つい話したくなって付け足した思い出話から、伊沢は僕の思惑を正確に読み取っていたのだろうと思うと、どうにも面映かったので。 悠季は僕の願いどおりに買い物や飾り付けを楽しんでくれて、石田氏に貰ったという小さなヴァイオリンをいそいそと吊るし、最後に笑いながら僕の肩車に乗って天辺の星を飾り付けた。 FINE 2007/12/13 |