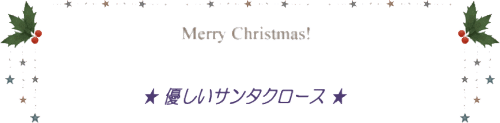 (1) 何かの拍子に「ああ、今年も終わりだな」と感じる瞬間がある。きっかけは色々、人それぞれだと思うけど、僕らの場合はやはり仕事の予定で埋まったカレンダーを見る時だ。シーズン中でもとりわけ忙しいトップシーズンであるこの時期は、通常の定期公演に加えて特別公演が目白押しで、それに伴う打ち合わせだの練習だのゲネプロだので隙間なく埋まるって感じになる。僕はまだそこまで忙しい思いをしたことはないけど、売れっ子の圭は普段だって過密なスケジュールが超過密って具合に忙しい。たぶん感慨に浸る暇なんかないぐらいに。それでも、年末恒例の第九の演奏会が近づいてくると、これさえ終わればちょっとひと息吐けるな、とは思うらしい。今年、M響の第九特別演奏会は、クリスマスを挟んで前二日、後一日の都合三日間公演で、例年より少し早めの日程だ。その分、年末はゆっくり休めるんじゃないかな、と圭の身体のことを考えると良かったと思ったし、僕自身も嬉しいと思っていた。 ところが――― 十二月に入り、今年が残り少なくなるにつれて、圭はだんだん不機嫌になっていった。初めのうちはポーカーフェイスで取り繕っていたのが今はもう隠そうともしないで、僕を相手に時々愚痴ったりもする。原因は、第九演奏会の狭間の一日、クリスマス当日に客演で振ることになっているコンサートだ。浮世のしがらみってヤツで断れなかったのだというそのクリスマス・コンサートは、M響が定期公演でも使っている都内の某ホールで行われるんだけど、圭はどうもそのコンセプトが気に入らないらしい。 「圭、箸が止まってるよ。お腹いっぱいなら無理して食べなくていいからね」 箸を持った手をテーブルの上に置いたままぼんやりと宙を睨んでいる男に、またか、と思いながら声をかけた。 「……ああ、いえ、すみません、せっかくのきみの手料理を。いただきます」 慌てて煮物を口に入れ、噛んで飲み下すや「美味いです」と笑って見せた圭を、僕は苦笑で許してやった。 これまでにもポツリポツリと零しているのは聞いたけど、食事も疎かになるほどモヤモヤを抱え込んでいるのなら、なるべく吐き出させてやった方がいい。僕は気が済むまで圭に愚痴らせてやろうと思って水を向けた。 「また例のコンサートのことを考えていたわけ?」 「はぁ」 「一旦引き受けちゃったものはしょうがないじゃないか。それともステージに穴を開ける?」 「それが出来れば苦労はしません。しかしどうにも気が進まないのですよ。ミーハーなお祭り騒ぎの片棒を担がされるかと思うと」 「なまじ売れっ子になるのも、ホント困りものだよねぇ」 当たり障りなくそう受けてやってから、続けた。 「なんとか気分を変えるしかないんだろうねぇ。嫌々振ってたんじゃ、いい音楽なんて創れっこないもんな」 「ええ、そんなものを曝すなど、僕の矜持が許さない」 圭は眉間にクッと皺を寄せたまま頷いた。 圭が言う『ミーハーなお祭り騒ぎ』とはこうだ。 日本のクリスマスは本来の宗教行事からかけ離れ、なぜかカップルのイベントと化している。高級レストランで食事をして豪華ホテルに泊まりムード溢れる夜を過ごす、というのが定番になっていて、学生から中には熟年層まで猫も杓子も状態だから、当然需要は鰻登り。どこのレストランやホテルも目の玉が飛び出るような値段の特別プランとやらを、ここぞとばかりに売り出してくる。圭が振る『恋人たちのクリスマス』と銘打たれたコンサートも、そんなクリスマス商戦に便乗したとしか思えない部分があるのだった。 何しろ、ホールのすぐ隣にあるホテルが、そのホテルでのディナーと宿泊にコンサートのチケットまでセットにして売り出したっていうんだから。もちろんレストランの座席には限りがあるから、圭が言うところのミーハー組はほんの一握り。普通にコンサートだけ聴きに来るお客さんの方がずっと多いんだけどね。 「まるで流行歌手のディナーショー扱いですよ。抜け目がないにもほどがある」 圭は吐き棄てるように言った。 確かに、ホテルの大広間にオーケストラを持ち込むのは無理があるから、ホールに隣接する立地を生かした、このホテルならではの目玉商品にはなっただろうけどね。 「でもさ、きみの音楽聴きたさに、何を置いても駆けつけてくれるお客さんもいるわけだろ? 何しろ桐ノ院圭は、僕が誰よりも尊敬する世界的人気の天才指揮者だからさ」 「最愛の、とは言っていただけないのでしょうか?」 「うふっ、言わなくても判ってるじゃない」 言って下さい、と強請る拗ねた目に負けて「誰よりも愛してるよ」と囁いた。食事中にはご法度かもしれない小さなキスを添えて。 テーブルの上に身を乗り出してそれを受け止めた圭は、短いため息を挟んで言った。 「確かに、大多数の客は演奏を聴きに来てくれるのだと思います。ですが、コンサートのタイトルといい、開演時刻といい、ホテルプランの利用客を重要視したとしか思えないのですよ。お陰で僕の帰宅は日付が変わってしまいそうだ。きみとクリスマスの乾杯をすることすら出来ないかも知れない」 やっぱりそこか、と思って込み上げてきた笑いを、僕は俯いて隠した。 「まあね、欧米じゃ普通だけど、日本だと珍しいよね」 ディナーの後になるコンサートの開演は20時。19時が一般的で、たまにちょっと遅くて19時半ってのもあるけど、それらに比べたら、やはり遅い開演だと言えるだろう。これが休日だったらマチネにして順番を逆にするところだったんだろうけど、あいにく25日は平日だ。 「クリスマスだからと、ディナーショー代わりに普段は聴きもしないクラシックのコンサートにやって来た軽薄な連中の為に、なぜ僕がムードを盛り上げてやらなければならないんです? しかも、きみとのクリスマスデートを犠牲にしてですよ!?」 あー、はいはい。 クリスマスは仕事で潰れると諦めがついてる音楽家家業のくせに、今更それを持ち出してゴネてるのは、要するに僻んでるわけね。他のカップルは、目の前で幸せそうにイチャついてるのに、ってさ。 「あのさ、圭、昔のことを持ち出すのもなんだけど、きみが言う軽薄な真似を、きみも昔やったって覚えてる?」 圭は虚を衝かれたって顔でしばらく僕を見て、それから「ええ、覚えてます」と噛みしめるように頷いた。 「僕らが出逢った年のクリスマスだったよね。確か女の人が歌うシャンソンだった。きみさ、あの人の歌が聴きたくて僕をディナーショーに誘ったのかい?」 「いえ、きみとの特別な夜の演出として、です。聴いた後で、そう悪くもなかったと安堵しましたが」 「うん。あの夜僕はさ、すごく緊張もしてたけど、心の中で何度も『夢みたいだ』って呟いてたよ。きみがプレゼントしてくれた上等のスーツを着てさ、一流ホテルで豪華な食事をして、美味しいお酒を片手に生演奏を聴いて。しかもさ、隣には僕を心から愛してくれている最高にハンサムでカッコいい恋人がいるんだぜ? どれもこれも僕には初めての経験で、最高のものばかり集めて紡ぎ上げたような時間で……ああ、これが特別な夜ってものなんだなぁ……きみと過ごせて幸せだなぁ……出逢えてよかったなぁ、って思った」 「悠季……」 「もしもあの時の食事が不味かったり、ホテルの雰囲気が悪かったり、あの歌が…聴くに堪えないほど酷かったり……そんな風にどれかが欠けてたら、僕はあれほどうっとりと夢心地にはなれなかったかも知れない」 圭は真っ直ぐな瞳で僕を見つめていた。僕の言いたいことを察している目だ。 でも僕は、それを口に出して言うつもりはない。言うまでもなく圭も解っていることで、だから葛藤しているんだと僕にも解るから。 お客が求めるものは、ディナーショーとコンサートでは違うのかも知れない。人それぞれ、多種多様の期待を抱いてもいるのだろう。けれど演奏する側のプロにとっては、ショーの歌手だってオーケストラだって、やることは同じ。何を求めてやって来たお客に対しても平等に真剣に、懸命に創り上げた自分の音楽を差し出すだけだ。 そして僕らは、そのプロの演奏家なのだ。 僕らのコンサートに来てくれるお客のすべてが熱心な僕らのファンだなんてことはないし、興味本位で覗いてみた人や、時にはとても音楽を聴きに来たとは思えない人だっている。それでも僕らは、いつだって真剣に精一杯の演奏をしてきたのだから。 「言ってみればさ、サンタクロースだよね、きみは。クリスマスの夜にコンサートを聴きに来た人みんなに、素晴らしい音楽と幸福な気分をプレゼントするんだ」 「サンタクロースは良い子にしかプレゼントをあげないのではありませんか?」 「あはっ、普通のサンタはね。だからさ、きみは心優しいサンタクロースってところかな? 初めてクラシックのコンサートに来たミーハーなお客もさ、きみの素晴らしい音楽を聴いて、夢みたいだなって、うっとりするような最高の気分を味わうんだ―――あの日の僕と同じようにね。そして、そんな特別な夜の幸福な思い出は、きっといつまでも心に残る」 「僕が幸福にしたいのは、きみだけです。出来るなら僕自身だけでなく僕が奏でる音楽も、すべてきみだけに捧げたい」 「それって本気で言ってるなら、すっごい問題発言」 「本気も本気、大真面目ですとも」 圭はそれを片眉をひょいと上げて言い、手を伸ばしてきてテーブルの上の僕の手を掬い上げた。大きな手の中でしばらく手慰みのように擦っていて、フッと寂しそうな顔をした。 「ですから、きみが聴きに来てくれるなら、どんなにか救われるのですが……」 圭の予定はもう随分前にカレンダーに書き込まれていたので、僕はそれを見て自分の仕事を入れちゃったんだ。 「ごめんね。クリスマスに僕だけ休むよりはいいかな、と思ったんだよ」 きみは一緒に過ごしたがるに決まってるから。 特別な夜に、僕を独りっきりにすることを、きっと気に病むに違いないから。 圭は握ったままの僕の手を引き寄せて手の甲に口づけ、唇を押し当てたまま低く低く囁いた。 「きみの存在に……感謝します」 それから僕の手をきゅっと握り、僕も黙って圭の手を握り返した。 それだけで、きっと気持ちは通じ合っているのだった。 その夜、圭は腕枕の中に僕を抱き込むや、あっという間に寝入り、僕はそんな圭に心底安心した。元々寝付きが良くて、しかも身体はクタクタになるほど疲れているのに、この頃なかなか眠れずにいたようなので。 しっかりと抱き込まれている所為で顔を見ることが出来ない圭の、逞しい胸に頬を寄せて、力強く規則正しい鼓動と深く静かな呼吸を肌で感じているうちに、僕もとろりと眠たくなって。 眠りに落ちる前に(明日あたり宅島くんに電話して、念を押しておかなくちゃ)と思った。 思ったところで眠ってしまったらしい。 圭の温もりが導いてくれた眠りは穏やかに深く、僕はその夜、夢も見ないで熟睡した。 CONTINUATO 2007/12/23 |