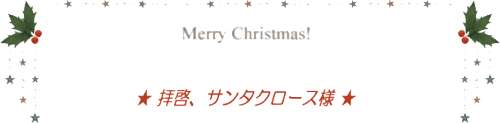 宴会が終わって店を出たものの、名残惜しくてそのまま店先でたむろする。飲み足りない、喋り足りない、楽しい時間をもう少し、と望む酔っ払いの姿があちらこちらで見受けられるのは、宴会シーズンの風物詩みたいなものだ。素面で側を通りかかる者にとっては、うるさいし、通行の邪魔だし、迷惑なことこの上ないんだけどね。 でも今夜の僕たちは、その迷惑な集団のひとつだった。 みんなに好評だったクリスマス会兼忘年会を、今年も開いたというわけ。ただ、ニコちゃんの店じゃ窮屈だったので、会場は富士見銀座にある馴染みの居酒屋にして、日程も大幅に前倒しした。クリスマスは家族や恋人と過ごしたいって意見があり、圭やM響さんたち『クリスマスは仕事組』も居るからちょうど都合が良かったんだ。かく言う僕も一応仕事組なんだけどね。 学生たちが幹事をやった今年の会は、子供も大人も楽しめるゲームが色々と企画してあって、とても盛り上がった。以前のように学生と社会人が線引きしたように分かれて固まるなんてこともなく、みんな本当に和気藹々って感じでね。楽しい時間が過ぎるのはあっという間だけれど、そんな風にいい雰囲気だったから尚更短く感じたんだろう。帰り際、僕は毎度お世話になってる店長さんに挨拶をしていたんだけど、その横をすり抜けていくみんなの表情は、誰も彼も名残惜しげだった。そうして最後に店を出たところで、僕はその光景に遭遇したのだった。 ほろ酔い状態の皆さんが、商店街の通りを塞ぎそうな勢いでたむろする姿。 ざっと見渡したところ、帰って行ったのは子供連れとシルバー組の数人ぐらいで、総勢七十名ほどの今夜の参加者が殆どそのまま。そして、幾つかに分かれてる話の輪の、一番大きくて一番賑やかな輪に、圭が捕まっていた。 「ねえねえ、桐ノ院さん! もう一軒行きましょうよ!」 「そうっスよ! こんな時ぐらい付き合ってくださいよ!」 「いえ、明日がありますので、僕はこの辺で」 「まだ時間早いじゃないですかァ」 「そうそう、こんなの宵の口ですよ! ねっ!?」 『捕まって』と表現したのは、周りを取り囲まれ口々に浴びせられる二次会への誘いを、圭が珍しくも断りきれない様子でいたからだ。 誘っているのは、圭のファンだと公言する女子大生連中だけじゃなく古参のメンバーも加わった顔ぶれで、皆一様にいつになく強引だ。それに、圭の方も苦笑って感じにポーカーフェイスが崩れていて、声を掛け易い雰囲気というか……昔の桐ノ院圭流に言うなら、不覚にも付け込む隙を見せてしまった、ってところだろうか。以前はあのポーカーフェイスでひと言言えば、それ以上は誰も何も言えない雰囲気になってしまっていたものだけど。 でも、そうなった理由に、僕はなんとなく察しがついていた。 今夜、和気藹々だったのは圭も例外じゃなかったからだ。 外見はいつもどおりで、澄ました顔もスマートな態度も崩さないんだけど、何ていうかバリアーみたいなものが消えていたっていうか、さ。子供の相手をしてやったり、敬遠気味だった学生連中にも混じって話をしたり、ゲームに参加してる時の様子だって、僕の目にはいつもよりもずっと寛いで打ち解けていたように見えた。そしてみんなも、それを敏感に感じ取っていたのだろう。 ああ、いいことだな、と僕は思った。 圭は元々人間嫌いって訳じゃないし、ずっと以前からフジミのみんなには、微笑んだり、嫌そうな顔したり、ふざけてみたり、と心を許していた。けれどみんなからすれば、まだまだ打ち解けてるレベルには見えなかったんだろう。なんせ感情を表に出すのも気持ちを伝えるのも上手くない、ホントに不器用な奴だから。こういう機会を切っ掛けに、ますますみんなと打ち解け合えたなら、それは圭にとってもフジミのみんなにとっても素敵なことだ。 圭は相変わらず「ですが」とか「しかし」とか、断り文句を言いかけては皆の言葉に遮られてる。妬けるぐらいにモテてるじゃないか、と思いつつ、「行っておいで」と言ってやらなきゃな、と思った。明日は朝が早いってことは知ってるけど、少しぐらいなら大丈夫だろうし、こういう機会は逃さない方がいい。あー、でも、僕が帰るって言えば一緒に帰って来ちゃうだろうから、一緒に行こうって言うべきか? 僕に気づいた圭が、助けてくれ、と視線を投げてきた。右手に荷物を持ち、空いた左手はコートのポケットに入れて突っ立ったまま、困り果てたような顔でチラッとさ。僕は笑い返しながら彼の方へ歩き出した。ところが、ちょうどその時――― 「ねぇぇ、桐ノ院さぁん、お願いですから〜ァ!」 業を煮やした女子大生のひとりが、媚びて甘えた声を上げながらしなだれかかり、圭の左腕にしがみつこうとした。 思わず、僕は声を張り上げていた。 「みなさ〜ん! 立ち止まらないでくださーい! 通行の邪魔になりますよー!」 ザワザワと談笑していた人垣が揺れる。 「はいはい、道の端に寄って〜ェ、歩いた、歩いたー!」 僕の促しに、「お疲れさまでしたー」「おやすみなさ〜い」と挨拶しながら半数ぐらいは散っていき、他にもゾロゾロと歩き出したけど、圭を取り囲んでいる輪はそのままだ。僕は続けて輪の中に斬り込んだ。 「あ、守村さん! 守村さんも行きましょうよっ!」 「コン・マス、是非ご一緒に!」 すぅ、と吸い込んだ息を一旦腹に溜めて、努めて平静に言った。 「えっと、皆さん二次会のご相談のようですが、今から飛び込みでこれだけの人数が入れる店なんて、この近くには無いですよ」 「ええ〜っ、でも〜、せっかくの機会なのにぃ〜」 ふくれっ面でブーイングを飛ばした一群に向かって、今度はにっこり笑ってやる。 「残念ですけど、適当にバラけるか新宿辺りまで繰り出すか、でしょうね。……ということで、僕は明日が早いので、すみませんがこれで失礼します。皆さん、お疲れさまでしたァ!」 皆に会釈して、圭の目をチラッと見てからスタスタと歩き出した。追いすがってくる誘いの声には、歩調を緩めないまま顔だけ半分振り返って手を振って。その途中で、「では」と短く挨拶した圭が当然のように後ろからついて来るのを目に収めた。ざわめきが少し遠のいたところで、タタタッと小走りの足音が追いついてきて、パシンと肩を叩かれた。 「よっ、守さん!」 輪の外側で終始傍観者を決め込んでいた飯田さんはニヤニヤ笑いを浮かべ、速足の僕らに歩調を合わせて歩きながら言った。 「面白いモン見せてもらったぜ〜」 「何がです?」 いつもの調子で答えたのは圭だ。 「うろたえる殿下に、ピシッと鮮やかな手並みで仕切る守さん。夫唱婦随の逆転ヴァージョン再び、だな。 なぁ、殿下?」 圭はムッと眉を寄せたまま黙り込んでいる。 再び、が何時のことを指して言ってるのか判らないでもないが、蒸し返されていろいろ言われるのはまっぴらだ。僕はぴたりと足を止めると飯田さんに向き直って、言った。 「僕らの場合はどっちの『夫』の字も同じですからね、臨機応変ってヤツですよ」 飯田さんはうっかり飴でも呑み込んだみたいに一瞬表情を失くし、それから腹を抱えて笑い出した。 「くくくくっ……あっはっはっはっ……リ、リバーシブル可ってかい!? いいねぇ〜、最高っ!」 僕好みじゃない暗喩はにっこり笑って受け流し、「それじゃ」と歩き出した。 「素敵な夜をなーっ!」と追い討ちしてきた声には、ひらひらと手だけ振って振り返らなかった。 ずんずん歩いて富士見銀座の突き当たりを折れ、国道沿いを行く間も、僕は黙って前だけを向いていた。圭が斜め後ろにピタリとついて来てるのは判っていたけど、肩を並べてお喋りしながらそぞろ歩く気分にはなれなかった。頭の中でグチャグチャに絡み合って収拾がつかない不快感を、なんとか解こうとしていたので。 やがて僕らの家が近づき、国道を折れて人気の無い住宅街の道に入ったところで、圭が話しかけてきた。 「悠季、怒っているんですか?」 「何を?」 「僕が、皆の誘いをきっぱりと断れなかったことです。その……情けないと、思っているのではありませんか?」 立ち止まって振り返った。 圭は、叱られた子供が親の顔色を窺うみたいな目で僕を見ていた。 「怒ってないし、思ってないよ」 では、どうして?と問いかける視線から、僕は目を逸らした。歩きながら考えてきたことは、まだ上手く言葉にならない感じだけれど、ひとつだけはっきりしてるのは、圭に非は無いってことだ。 「ごめん、八つ当たりだ」 深く吸った息を吐き出すタイミングで言って、回れ右して歩き出した。ゆっくりとした僕の歩調に圭はすぐに追いついてきて、今度は僕の横に並んだ。 僕の右側に圭。僕が好きな落ち着ける位置で、だから自然と僕らの習慣になった並び方。 コートのポケットに手を突っ込んだままの、触れ合いそうなほど近くにある圭の左腕に、そっと右手を絡めた。チラッと目が向けられたのを感じたけれど、圭は何も言わなかった。僕も前を向いたままで言った。 「気がついたかい? きみのこの腕に、しがみつこうとした」 ああ、だからだ。だから僕は、たぶん、あの時……理性を失った。 圭にもみんなにも良いことだって考えていたのに……。 「ええ、僕としたことが隙を見せてしまったようで……不覚でした」 「隙じゃなくてさ、それがきみの自然な姿だ。きみが本当のきみだったから、だよ」 「は?」 常時ポーカーフェイス着用が当たり前の男は、本当に解っていない顔で僕を見ていた。 無理も無い、か。 心を割って人と接し、関係を育む、ということを知らずに育った彼は、以前僕とやり合った時に、どこまでが真剣でどこからが冗談なのか―――誰よりも解り合っている僕を相手にしてさえ、その加減が判らなくて戸惑っていたのだから。 「みんないつに無く強引というか熱心にきみを誘ってただろ? あれはさ、きみが普段よりずっと寛いで打ち解けていたから、みんな嬉しくなっちゃったんだよ。」 「僕は、普段と何ら変わらずに振舞ったつもりですが……ああ、もしや、あのジョークがいけなかったんでしょうか?」 圭は右手に持った紙袋を掲げて心配そうに訊ね、僕はその時の様子を思い出してぷっと噴き出した。 今年、恒例のプレゼント交換には《その場で包みを開けて、もらった品物にひと言感想を言う》というルールがついていた。贈り物をもらったら、相手に対してお礼やら感想なんかを言うのは、ごく普通のことだからだ。圭がもらったのは、毛糸で編んだクリスマス・ソックス。あの、サンタクロースにプレゼントを入れてもらう為に用意する靴下だった。ただそれが半端じゃない大きさで、全長およそ一メートル五十センチ、足のサイズも五十センチは下らないという超ビッグサイズ。圭は手にした靴下をしげしげと眺めながら、真面目くさった顔で言った。 「とても暖かそうな靴下をいただきました。僕の足にはちょうどピッタリのようで……サイズが無くて苦労する身には、実にありがたい」 宴席がどっと沸いたのは言うまでもない。 「まあ確かに、あれも効いたと思うけどね。でも、それもさ、きみが自然体だったっていう基盤があればこそだよ。みんなきみのことは、我らが天才コンダクターって感じで敬愛してるけど、本音を言えばごく普通の友人のように、大好きなきみともっともっと親しくなりたいんだと思う。でもきみって奴は、どこか近寄りがたい雰囲気を纏っているのも確かでさ。だから今夜のように堅いガードが緩んだきみを見て、みんなが飛びついたのは当然だよ」 彼が創り上げてきた桐ノ院圭という人間像。それが少しずつ変化しきていることに気づいてないのか、あるいは漠然と感じて戸惑っているのか―――眉を寄せた困惑顔に、僕は笑って言ってやった。 「だからさ、いけなかったんじゃなくて、良かったんだよ。あのジョークも、きみが自然体でいたことも、ホントに良かったんだ」 そう、悪いのは僕だ。せっかくのチャンスを、子供っぽい嫉妬でふいにした。 この手を、彼を、僕だけのものにしておきたくて。 掴んでいた圭の左手を放したら、急に寒さを感じた。手袋をしているのに、手のひらも指先も冷たくて、そこから身体の中まで冷気が凍みてくるみたいに。 「悠季?」 訝しげに呼んできた圭に、俯いたままで答えた。 「ごめん、ちょっと、自己嫌悪。穴掘って埋まっちゃいたい気分だ」 圭は、僕が放した右手を捕まえて指と指を絡めてキュッと握りなおすと、そのままコートのポケットに導いた。 「確かに今夜の僕は、あの集まりを楽しんでいたと思います。二次会に参加してフジミの諸君と更に親交を深めるのも魅力的だと思えるくらいには。ですが、その機会は今後幾らでもあるでしょう。ともあれ、今夜は早く帰りたいと思っていた僕には、きみの機転と方便はありがたい救いだった」 手袋越しの僕の手を、長い指が愛撫のように優しく撫でている。つ、と顔を寄せてきて、艶のあるバリトンが耳元で言った。 「何しろ今夜は、明日がオフのきみと心ゆくまで親交を深めることが出来る貴重な夜ですので」 「……そ、それこそ! 今後幾らでも機会はあるだろうけどねっ」 言い返しはしたけれど、僕は内心で圭に感謝していた。あの場の僕の采配を肯定することで、圭は僕の狭量な振舞いを許してくれたのだろうから。 でも、もしかしたら、僕が独占欲を露にしたことを喜ぶ気持ちもあったのかも知れない。 家に帰り着き、玄関でコートを脱ぐまで、僕らはポケットの中で手を繋いでいた。 もらった大きな靴下を、圭はピアノ室の暖炉の横に吊るした。 僕が子供の頃には、欲しいものを書いたサンタさんへの手紙を中に入れて、ベッドの枕元に吊るすものだと聞いたんだけど(尤も、僕は布団で寝ていたので、枕元に置いていただけだったけど)、圭が知っていたのは暖炉の傍に吊るすって方法。言われてみれば、サンタクロースは煙突から入って来るわけだから、その方が好都合だよな。こういうものひとつ取っても、国や地方によって色々あるもんだね。 クリスマスが近づいたある日、僕は圭の留守に靴下の中の手紙をこっそりと盗み見た。勿論、クリスマスプレゼントの参考に、圭が欲しがっているものを知りたかったからだ。雪の結晶を散りばめた柄の綺麗なカードを開いて――― 中身を読むや、僕は一瞬絶句し、それから耳まで熱くなるほど頭に血が上るのを感じた。
こ、こンの〜〜〜〜〜〜ッ!! 正月用の餅をクリスマスの朝に焼いて出してやろうか!? と、僕は本気で考えた。 FINE 2007/12/17 |
||