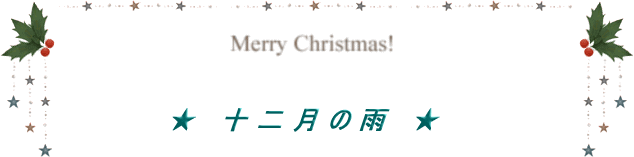 玄関のドアを閉めて外気を遮った途端、思わずほぅ、と息を吐いていた。室内の空気に触れて初めて、外の寒さを実感したのだ。 今夜も雨。冬の到来を告げるように、季節の変わり目にありがちなぐずついた天気が、ここ数日続いている。雨の持つ陰鬱で冷え冷えとした印象に加え、十二月の声を聞いて急に寒くなったように感じてしまうのは、多分に心理的なものもあるのだろう。一枚だけ残ったカレンダー、慌しく過ぎていく日々、クリスマス、そして、新年を向える準備。数々の師走の風物詩は、当然、寒さをも思い起こさせるものだ。 忙しさに拍車がかかりつつある日々を疲労も寒さも自覚せず淡々とこなしていたつもりだが、ふとこんなことを考えるとは、思った以上に参っているのかも知れない。 じっとりと濡れた傘を傘立てに押し込み、光一郎氏に帰宅の挨拶を済ませたところでパタパタと軽い足音が近づいてきた。 「お帰り。寒かっただろ?」 胸の内にポッと灯りを灯してくれるような微笑み。駆け寄ってきた勢いのままに、悠季は伸び上がって僕の唇にちゅっと口づけた。「ふふ、唇も冷たい」と呟きながらも身を寄せて、コートに散った雨粒をも厭わず僕を抱きしめる。華奢な身体がピクリと震えたのは、外気に曝されていたコートの冷たさがセーター越しにも伝わったからなのだろう。僕は抱きしめ返そうとした腕でそっと悠季の肩を押し離し、コートのボタンを外した。両手で前を広げて視線で誘うと、悠季はさも可笑しそうに笑いながら僕の懐に身を寄せてきた。 「ただいま帰りました。ああ、これでやっと暖かくなった」 ぴたりと身を寄せ合い、蓑虫のようにひとつコートに包まりながら再びセレモニーのキスを交わす。ふたりで温もりを培い、分け与え合う悦びに満たされる。ダブルのコートには多少のゆとりがあるとは言え、ふたり分の身体をすっぽり包むのは元より無理な話だ。だが、これこそ心理的なものが大きく作用している好例だろう。 「うふっ、ダブルのコートでよかったね」 「ええ、今後コートはダブルしか買わないことにしましょう。デザインが生まれた背景には、あるいはこうした使用方法が念頭にあったのかも知れませんし。 ああ、マントなどはより明確にそのような意図で作られたに違いありませんね」 真っ赤な嘘を、さも尤もらしく真顔で話してやると、悠季は僕の身体に小刻みな震えを伝えて来ながら腕の中で笑い悶えていた。 馥郁とした香りを立ち昇らせる熱いカップを両手で包み込む。 心地よく暖められた部屋で緩み始めた身体が、さらにほろほろと解けていく。 「風呂も沸いてるけどね、冷え切った身体でいきなり熱い湯に入るのは良くないんだって。だからまずはコーヒーでも飲んで、ひと息ついたら?」 そう僕を気遣って、悠季が設えてくれたコーヒーブレイク。 同じ豆、同じ器具を使っていながら悠季が淹れるコーヒーは僕のそれよりもまろやかな味わいで、いつも癒されるような心地がする。そこには淹れ方の上手下手といった物理的な要素だけでなく、悠季の優しい人柄といったものも反映されているように思える。それに、最愛の悠季が僕の為に淹れてくれた、という心理も、大きなプラス要因として働いているに違いない。 ヒトの感覚とはなんとも曖昧で、そして、なんと心理的な要因に左右されるものだろう。 「不味かった?」 ぼんやりとしていた僕を、気遣わしげに覗き込んでくる。 眼鏡の奥の柔らかい茶色の瞳を、微笑んで見つめ返した。 「とんでもない! 美味いですよ。 きみが淹れてくれるコーヒーは、どうしてこんなに僕を癒してくれるんだろう、と考えていました」 悠季は破顔して、照れながらも少し得意そうに言った。 「そりゃあね、僕の愛情がたっぷり込められてるから」 「なるほど。では、相乗効果の賜物ですね」 僕は先ほどからつらつらと考えていたことを話し、悠季はそれを聞き終えると、ふぅ、と一息吐いて言った。 「要はさ、気のせいってヤツだろ?」 ―――きみはなまじ頭がいい分、難しく考え過ぎちゃうんだよ、と笑う。 「でさ、僕らはそれを知ってて、上手い具合に生活の中に活かしているわけだろ? 寒い冬には暖かい色合いのカーテンに替えてみたり、とかさ。ああ、気のせいって言うとマイナスっぽいイメージだけど、なんて言うか……うん、気の持ちようって言えばいいのかな?」 「より幸福に生きるための、心の自然な作用ですかね」 「うん、そんな感じ。でもさ、なんでまた急にそんなことを考えちゃったわけ?」 「あー、最初は何だったのか……。きみが居るこの温かな家を離れて、冷たい冬の雨が降る中を明日も仕事に行かなければならない、という遣る瀬無さだったのかも知れません」 また子供じみたことを、と笑われるのを覚悟で僕は正直に言った。 悠季は一瞬顔を歪めただけで、あの慈愛に満ちた微笑を浮かべ、カップを置いた手で僕の肩を抱き寄せた。 手遊びのように肩口を撫でている指先が、口に出さない慰めを伝えてくる。 ―――忙し過ぎて心が疲れているんだね、とでも言うように。 だから悠季が次に言った言葉は、僕には随分と唐突に思えた。 「山茶花梅雨、って言うんだってさ」 「は?」 「この季節の長雨のこと。ほら、春先のは菜種梅雨って言うだろ? ちょうど菜種の花が咲く頃だからさ。あれと同じで山茶花の咲く頃だから、なんだって」 話の意図が読めず、頭を起こして向き直った僕に、悠季はほんのりと笑って続けた。 「雨がまったく降らないのは困るけど、長雨はやっぱり憂鬱だろ? だからさ、その時季を少しでも気分良く過ごせるようにって……さっきの話みたいに、誰かがそんな風に考えて名づけたのかも? な〜んてね」 「ああ、確かに。雨の中で咲く花の姿を思い浮かべれば、風流な気分にはなれますね」 「あは、うん」 悠季は柄にもないことを言ってしまったというように頻りに照れていた。 恐らくは名前の由来の真相も違うものなのだろうが、そんなことはどうでもいい。僕への慰めを懸命に差し出してくれている悠季の気持ちが、僕は何よりもありがたかったのだ。 「山茶花ですか……」 どんな花だっただろう、と咄嗟には思い浮かばずにいた僕に、悠季は駅に行く途中にある家の生垣に咲いていると、その家の場所を示して教えてくれた。ウエーブを描きながら幾重にも重なった純白の花びらを、美しいと思いつつ通り過ぎた記憶がある。 「では、明日は雨の代わりに白い花びらが降っていると思って歩いて行きましょう」 「うわ、想像するとすごい光景だけど、きみだときっと絵になるね」 「あの清楚な花には、きみの方が余程似合いますよ。ご一緒にいかがです?」 「あは、そういえば明日はきみと同じぐらいに家を出なきゃな」 「では、傘を並べてご一緒に」 「うん。じゃあそろそろ休まなきゃね。これは僕が片付けるから、風呂に入っちゃいなよ」 悠季は立ち上がってふたつのカップに手を伸ばしたが、僕は自分の分を持って立ち上がった。 「よろしければ、片付けも風呂も、ご一緒に」 肩を並べてカップを洗い、一緒に風呂に入って、一緒にベッドへ潜り込み――― 悠季の穏やかな寝顔に僕もまた眠気を誘われながら、微かに届く雨音を聞いていた。 暗い空から降り続く銀の糸は夜が明けるにつれて純白の花びらに変わっていき、僕らは傘を並べてその中を歩いていく。 そんな幸福な空想は眠りの中にまで続き――― いつしか山茶花の雨は、チャペルの前で手を取り合う僕と悠季に降り注ぐライスシャワーに変わっていたのだが、それは当分の間、悠季には話さない方が良さそうである。 FINE 2007/12/04 |